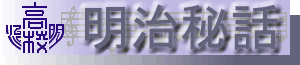 |
|
|||
| 校歌の秘話 |
| 2001年度 明治大学附属明治高等学校中学校生徒会誌 |
|
吾等が明高生の愛唱歌といえば何と言っても、「白雲なびく」ではじまる校歌であろう。 読者にも覚えがあるのではないか。普段、クールで愛校心なんて持ってないよという素振りを見せていた この壮大な愛唱歌は、それにふさわしいドラマチックな歴史を持ち合わせていた。その歴史は、明治という学校の歴史そのものであった。そもそも明治の校歌はなぜつくられたのか。この問題を語るときに、ライバル早稲田の存在を無視することはできない。 我々の感覚だと学校に校歌があるのは当り前のようにも思えるが、明治の校歌が作られた大正9年、校歌は必ずしも全ての学校にあるものではなかった。 明治と早稲田はよきライバルであり、ボートレース、野球などで対戦することも多かった。 早稲田の学生は試合のヤマ場になると必ずといっていいほど、肩を組んで校歌を歌い出す。 ちなみにこの「都の西北」という校歌は坪内逍遥、島村抱月といった大学の人間が、OBの芸術家である相馬御風、東儀鉄笛に依頼して作ったものである。 明治の学生はその光景を見るのがなんとも悔しかった。自分の学校に校歌がないというだけで、早稲田の人間に負けたような気がした。そんな現実を変えるため、校歌を作ろうと立ちあがった人物がいた。 武田孟、牛尾哲造、越智七五三(しめきち)の三人である。 武田、牛尾、越智は商学部予科の学生であった。彼等は大学に交渉し、校歌を学生の手で作って良いという承認を得た。大正9年のことだった。 彼等は予科の教授の紹介で詩人の児玉花外に作詞を依頼した。花外は「社会主義詩集」などの代表作を
もつ著名な詩人だった。 早稲田の例とは隔世の差がある。彼等が交渉に苦労したことは想像に難くない。 しかしながら花外は快く了承した。これは慈善事業というわけではなく、残りの人生を明大校歌に捧げるといった、気概あふれるものだったという。 |
|
花外は武田らと共通点が多い。酒好きの武田、重い社会的責任を負いながら経済的に恵まれない医者の父を持つ牛尾、小樽を愛した越智・・・。花外はそんな彼等に魅力を感じたのであろう。 わずか数日後に、花外は詩を完成させた。
この景気のいい詞に3学生も花外も大満足した。 |
|
ところが困ったことが起きた。耕作が、「詞を書き直したい」と言い始める。 すると花外は快く「書き直してください」と答えた。花外の人間的魅力を感じさせるエピソードである。 詞はこの後耕作らによって書き直されるから、実際の作詞者は花外ではない。今日明治の校歌の作詞者は花外とされているが、これも正しくないということになる。しかし、このやり取りなどを見ていると、花外の名が残って良かったという気持ちになる。 さて、耕作は詞を書き直すことになるのだが、これは耕作の専門外の分野であり、製作は容易ではない。にもかかわらず、彼は20日で作詞を完成してしまった。 そこには毎朝6時に耕作の家の門を叩いたという牛尾の熱意があった。牛尾にしてみれば、花外が詞を書き直すことを許してくれた、その温情に答えたいという気持ちでいっぱいだったのだろう。 耕作もこの牛尾の熱意には心を動かされるものがあったらしい。校歌の一節に「文化の潮みちびきて」とあるが、牛尾というこの男に耕作が敬意を評して同じ音を持つ「潮」という言葉を校歌に組み入れたという。 耕作の作った歌詞は次の通りである。(1番のみ)
さて、耕作はこの詞を完成させた後さらに一人の詩人を紹介した。 |
| この八十も文学史上に残るほどの偉大な詩人である。
まさしく現在の明治の校歌である。 これを作ったのは花外ではなく耕作でもなく、西條八十という男であった。 作曲は山田耕作が行った。とはいっても、現在の校歌のメロディーは本来ベルギーオリンピックに出場する選手を激励する為に作られたものだった。牛尾が耕作を説得してこの歌をもらったのだという。 かくして明治の校歌は作られたのであった。 明治の校歌は、ただの一学生に過ぎない男達によって作られたものだった。彼等の「学生の心を一つにする校歌を作りたい」という思いが困難を乗り越えさせたのだ。 | |
| そしてその校歌は、完成から80年を過ぎた今でも我々の心に響いてくる。 この原稿を書くにあたって、軍司貞則さんの「おお、明治 白雲なびく校歌誕生物語」を参考にさせていただきました。 |