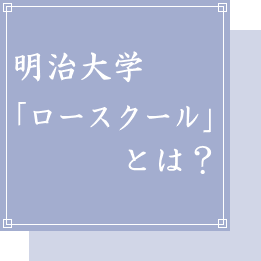 |
明治大学は今、大学改革の渦中にある。 平成十四年四月には新学科が四つも増え、 生涯教育の場としての校舎建築が進むなど、 それはとどまることを知らない。 そんな改革の一つとして、大学では 法学部を中心に、平成十六年四月に 「ロースクール」設立を目指している。 今までの大学院での法学研究科とは 一線を画す講義・指導が行われるようだ。 その実態を、法学部長の納谷廣美氏に インタビューしてみた。 |
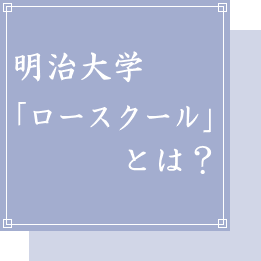 |
明治大学は今、大学改革の渦中にある。 平成十四年四月には新学科が四つも増え、 生涯教育の場としての校舎建築が進むなど、 それはとどまることを知らない。 そんな改革の一つとして、大学では 法学部を中心に、平成十六年四月に 「ロースクール」設立を目指している。 今までの大学院での法学研究科とは 一線を画す講義・指導が行われるようだ。 その実態を、法学部長の納谷廣美氏に インタビューしてみた。 |
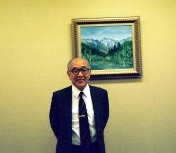
納谷廣美 法学部長
M編集委員(以下M)
まず、「ロースクール」を設立するきっかけは何だったのでしょうか?
納谷法学部長(以下法)
明治大学も、これまで大学改革の中で、大学院のあり方が問われていました。というのも、昨今グローバル化が進み、日本という国も世界での役割が大きくなったためです。そこで法の世界でも、その役割を担う、又はこれを支えていく人材の養成が必要になったのです。
その必要性は、中教審(中央教育審議会)や司法制度改革審議会といった機関においても指摘されてきました。そこで大学では、国際競争力を強める質の高い人間を育てるために、高度職業人養成型の専門大学院を作ったらどうだろうか、という提案が挙がり、その具体化の動きの一つとして、この「ロースクール」の設立があるのです。
M
では、司法試験に対応するだけでなく、世界の弁護士・裁判官等を目指して、指導していく方針になるのでしょうか?
法
そうですね。今まで予備校に委ねていた法曹人(法律に関する仕事を専門とする人)の育成を、本来担うべき教育機関である大学が「ロースクール」という新組織のもとで手がけていくことになります。
M
「ロースクール」と従来の予備校の違いを教えていただきたいのですが。
法
従来の予備校は、司法試験を前提にした指導のみを行ってきました。しかし、そのような指導では試験に出るところを中心に学習させるので、問題をよく考えたり、分析することができない法曹人を生んでしまいます。
「ロースクール」は、そのような弊害を防ぐために、法曹養成をプロセスとして再構築し、その重要な柱に相当する基礎部分を学ぶ場になります。法制度の背後にあるもの、例えば、人間の生活を支える歴史や宗教などを学ぶ、ということを通して、現行の(法理論と法律実務を架橋する)ところ、人の身体に例えると延髄に相当する部分を学習する場になります。
また、特色ある教科をカリキュラムに設けています。本学の場合について例を挙げれば、「医療・生命倫理と法」、「ジェンダーと法」等といったもので、全て新しい法の問題を取り上げたものです。
このように幅広い分野を教えることで、大きな変化に対応できる法曹人の養成を目指していきます。将来は、卒業生の七〜八割が司法試験に合格できるようにしたいと思っています。
M
「ロースクール」の入学対象者は?
法
大学を卒業した人は、どの大学・学部であっても入学ができます。また、社会人の入学者も募集する予定です。現在の予定では、一学年で約百五十名を予定しています。
M
修業年数が三年間と二年間に分かれるようですが?
法
標準は三年間です。しかし、法学部出身者などの法学既修者については、二年間で卒業できるコースも設けてあります。
法学未修者、または一から法律を勉強し直したい人は、一年間増やして法律科目の基本からしっかり学習することができるのです。
室内から建設中のB地区を撮影
M
校舎はどこが予定されるのでしょうか?
法
現在建設中のB地区(写真参照)校舎を予定しています。B地区は「生涯教育の場」として、「ロースクール」以外にも幅広い分野で使われる教育施設になります。
M
では最後に、この記事を見ている付属の中学生・高校生に向けてメッセージをお願いします。
法
若いうちは、何でもやりたいことにチャレンジして欲しいと思っています。例えば、勉強・スポーツ・音楽など、何でもかまいません。
そこで、挫折することもあるでしょう。でも、難しい局面の問題にぶつかることを恐れずに、なおかつ、その痛みが分かる人間になってもらいたいと思います。そこから、どんな変化にも対応できる強い人間が生れると思います。
付属生だからこそ受験勉強だけでなく、熱中できるものを大いに探して欲しいと思います。
| 法律専門学校やいわゆる予備校とは一線を画した、新しい職業人養成型大学院、 それが「ロースクール」である。 二年後の開校を前に、早くも他大学・他学部から注目の目を浴びているようだ。 今後の活動が、期待される。 |