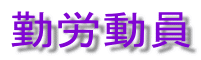
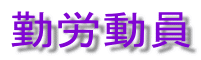
程なく学校内の授業は中断され、学外での「勤労動員」が始まった。
戦禍著しい焼け跡の整理である。
私たちが派遣された地区は浅草地区であった。集合場所は浅草区役所前。
先ずは、ここから徒歩で鳥越神社跡に向かう。神社の鳥居が無残にも半壊状態で倒れている。まだ燻っている煙が鼻をつく。手拭いで鼻を覆い、トタン板や、曲がりくねった針金や電線等を一ヵ所に集める。汗が滲み、擦ると煤で顔が真っ黒になる。
刀剣店の跡だろうか、無数の刀が出てきた。勿論焼け焦げて、とても使い物にならない。それでも一人が、その中の一本をこっそり懐にしまいこむ。
こちらは酒屋の跡か?掘ってみると、塩が大量に出てきた。これまた焼け焦げの匂い夥しい塩であったが、戦時下貴重な調味料である。一同歓声を挙げ、我先に掘り出そうとしたが、間髪入れず近藤隊長(後述)から命令が下る。
「一ヵ所に集めろ!」
掘り出された塩は、思ったより大量であった。
「欲しい者は一列に並んで空の弁当箱を出せ。家で喜びますぞ」
隊長に言われ、並んだ順に一掴み程の塩が弁当箱に入れられた。だが一様に不満気であった。皆に分配した後、かなり残った筈だが、あの塩は一体どうなったんだ?…一同、詮索することも忘れなかった。
後日、勤労報奨が出た。日数に応じて、一日玄米半合・大豆半合が学校から支給されたのである。その量はかなりのもので、どこの家族も大喜びだったに違いない。玄米を一升瓶の中に入れ、棒を突き刺して上下させると、糠が落ち精米されて白米に一変する。これも当時の「生活の知恵」だ。久し振りに食べた銀シャリ。おかずは沢庵に梅干し、精々鰯の干物だったが、あんなに美味いメシを食ったことはない。
食料だけではない。往復交通費も経路によって、それぞれに日数分が支払われた。これも中学生にとってかなりの金額であった。後日クラス仲間に尋ねてみると、殆どの者が親には内緒で懐にしまいこんだそうな。何に使ったかは記憶の外だが、いやはや親不孝共の集まりではある。
こんな恩典もあった。観劇招待券の配布である。この戦時下、空襲の連続、いつ爆弾投下があるやも知れぬ状況下、浅草六区の劇場では舞台公演が行われていたのである。
常盤座では杉山昌三九・本郷秀雄の「鞍馬天狗」。松竹劇場では、水の江滝子・タンポポ劇団の「冒険活劇」(題名不詳)等。何れも大がかりな仕込みの舞台であった。
今考えると、誠に不思議な話だが、ウソのようなホントの話なのだ。
然し、浅草焼け跡整理の往復時や、登下校の際、生命に関わる事も少なくなかった。
ある一人は、学校に近い駿河台に住んでいた。そこで野木教頭から連絡員に任命された。作業地に向かう前に予め伝達辞令を受け、作業後は戻って、当日の状況報告をするのである。
ある日作業の帰路、蔵前から御徒町駅方向に歩いていると、突然、上空から鋭い急降下音が響いてきた。W状の翼で米軍の戦闘機と分かった。彼は咄嵯に、目にした防空壕の中に飛び込み、身を丸めた。その刹那、激しい機銃掃射の音が耳をつん裂いた。暫く防空壕の中に伏せたままで蹲って居たが、それは短くも長い時間だった。
やっと我にかえり、壕の中の異常なまでの臭気に気づくと、振り向き声を挙げた。黒焦げになったミイラと思しき遺体が重なり合っていたのだ。ゾッとして外へとび出したものの、またも危険を感じて道路の脇に身を伏せた。そっと空を見上げれば、米軍機は既に飛び去った後で、余りにも青い…とても地獄とは思えぬ…真っ青な空だった。
或る一人は、久しぶりの教室でのこと。警戒警報により授業が中止となり、水道橋駅方面に向かっての下校途中だった。駅近くまで来ると、空襲警報のサイレンが鳴り、人々は避難場所を求め右往左往の状態となった。線路高架下には兵隊が多数集結してる。彼も足早にその場へ近づいた。ところが、兵隊の一人が彼の行く手を阻止するのだ。それは殆ど怒号に近かった。
「こっちへは来るな!我々が居るから却って危ない!そっちへ行け!」
怒鳴られ、彼は兵隊の示す方向へ一散走りに走った。その直後、米軍機の急降下音と共に、機銃掃射の炸裂音が鳴り響き、辺りは忽ち阿鼻叫喚の巷と化した。
彼は述懐する。自分を阻止してくれたあの兵隊の怒号が無かったら…。私は、現在生きていなかったかも知れない……。
これまた余談だが、当時、後楽園球場の上階には、対空用の高射砲陣地があり、その近くに軍の特殊兵器研究所もあった。当然、軍上層部だけしか知らぬ極秘の施設である。
各大学から、科・化学の優秀な人材が集められ、新兵器の開発や、特殊シェルターの研究に明け暮れていたという。気流に乗せて飛ばす風船爆弾などはまだ増しな方で、殆どが実用には程遠い、珍無類のものばかりだったという。だが彼等の実態は、将校相手の麻雀や飲酒で暇を潰したり、一日中腕組みで思考する態度をしていれば、それで一日のお役目は終わったという。報酬や待遇も良く、酒や食べ物も上等で、終戦を迎える日迄は、正にこの世の極楽であったそうな。
尤も終戦間際、特殊シェルターの案件には、一同襟を正しての真剣な討議が為された。皇居から富士山麓に通ずる隧道の施設計画である。目的は言わずもがな。残念?ながら、これは構想だけで終戦を迎えてしまった。
この話は、K県K市の博物館勤務の技師から聴取した懐古談であるから、真実に相違無い。
|
こんな事もあった。 私たち1年生は、全員体育館下の前に集められた。教練の将校が蛮声を挙げる。 「これより倉庫内に保存してある銃を運び出す。全員手分けして運び出し作業に掛かれ!」 三挺ばかり以外は殆ど使用に耐えない古びた三八銃である。これを全員で運び出すと、 「各自一挺づつ持って、校庭に集合!」再び命令が下る。 「全員整列!担(にな)え銃(つつ)!」 不動の姿勢をとり銃を肩に担ぐ。戦闘帽(徽章は陶製)をかぶり、カーキ色の国民服を着てゲートルを巻いているから、一寸見には、まるで小さい兵隊のようだ。 理由はこうだ。「使用可・使用不能に拘らず保管されている武器を全部献納せよ」と、軍部から各学校に供出通達があったのだ。 察するに、兵器不足の折から、これらの古い銃器等を再生し、戦場へ回そうと言う魂胆らしい。行き先は信濃町の近衛第四師団、神宮球場の間近にある。 そこで我らチビッコ部隊は、堂々粛々隊列を組み、先ずは御茶の水駅に向かって行進を開始した…などと…そんなに格好良いものでは無かったが、駅から省線電車(JRの当時の呼び名)に乗り込んだ。 たまたま車内に、見るからに品の良い老婦人が乗り合わせていた。その婦人が我ら勇士の胸の名札を見ると、目をしょぼつかせ、ハンカチで涙を拭きながらこう言った。 「まあまあ…可哀相に…-あなた方のような一年生までが…-」 私たちが戦場へ駆り出されると勘違いをされたか。それとも、ご自分の境遇が重なって、涙を流されたのであろうか。 |
 |